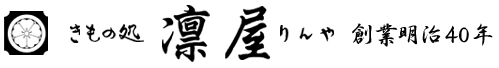![]()
「花嫁のれん」は、幕末から明治時代初期の頃より、加賀藩の能登・加賀・越中に見られる、庶民生活の風習の中に生まれた独自ののれんです。
それは嫁入り道具の一つであり、実家の家紋が二つ染め抜かれた、華やかなのれんです。
花嫁が嫁入りのときに「花嫁のれん」を持参し、花婿の家の仏間の入り口に掛けられます。
玄関で合わせ水の儀式を終え、両家の挨拶を交わした後、花嫁はのれんをくぐり、先祖のご仏前に座ってお参りをしてから結婚式が始まるというものです。
その後、「花嫁のれん」は新婚夫婦の部屋の入り口に掛けられ、三日目にお部屋見舞いの仲人や親戚の女性が集まり、花嫁持参のお道具や衣裳のお披露目の時に花を添えました。
現代では、風習・しきたりを重んじる地域の旧家や石崎奉燈祭等の祭礼時には、欠くことのできないものとして、その家々にて大切に受け継がれています。
合わせ水の儀式とは
花嫁は生家の水を竹筒に入れて持参し、嫁ぎ先の水と、玄関先でカワラケと言われる素焼きの杯に同時に注ぎ、花嫁がその水を飲んだ後、二度と繰り返さないようにとの意味合いから、その杯は仲人夫人によって地面に打ちつけられ割られます。

結界を越える花嫁
花嫁のれんは、横幅約180~190cm(反物の生地巾5枚分)、縦の長さ170~180cmで、襖2枚分の大きさに相当します。
通常、仏間の入り口の襖4枚の中2枚を開いた空間に掛けられ、花嫁がくぐって入り仏前に座り「ご先祖様、今日よりこのうちの者となります、どうぞ宜しくお願いします」と手を合わせ、ご挨拶をする「仏壇参り」という儀式に使用されます。
清浄な領域を生み出す花嫁のれん(=結界)の内に入った時、花嫁の新しい人生が始まります。
母の花嫁のれん
結婚式当日の朝、婚家へ向かう前、花嫁は実家の仏壇に手を合わせ「ご先祖様、今日までお世話になりました。
本日、私は嫁ぎますが、これからもどうぞお見守りください」とご挨拶をし、生まれ育った家を出ます。
その時には箪笥に眠っていた、数十年前にその家に嫁いできた母の花嫁のれんをくぐって縁側から出ます。
(玄関からではない理由は、玄関は出入りをする場所なので、「出たり入ったり」をしないように、という風習です)
母ののれんは、娘に持たせ受け継ぐのではなく、その嫁いだ「家」に代々受け継がれていきます。花嫁のれんは「もう後戻りはできない」という女性の決意ののれんなのです。

なぜ「のれん」か
「のれんが風になびくように、婚家の家風に早くなびき(馴染み)ますように」との意味があります。
また、仏壇に参る前にのれんをくぐることによって、頭についた穢れを払う、ともいわれています。
いずれにせよ、花嫁と婚家を結ぶ、架け橋となるのが「花嫁のれん」です。
何はなくとも「花嫁のれん」だけは
ほかのどんなお道具が用意できなくとも、花嫁のれんだけは必ず持たせたという時期もありました。
実家の家紋が染め抜かれたのれんは、慈しみ育てた嫁ぐ娘の幸せを願う両親の心です。
現代の花嫁のれん
今も脈々とこのしきたりが残る七尾近辺では、近隣地域同士の婚礼には欠かせないものとして、大切にされていますが、花嫁のれんの元々の発祥の地である金沢では、都会化した故にその風習は薄れて今では少なくなってしまったのが現状です。
その一方で、結婚式場に花嫁のれんが飾られ会場に花を添えたり、披露宴にて新郎新婦が花嫁のれんをくぐって登場する演出として用いられるなど、異なった形でこの風習が見直されつつあります。
時代の変化とともに失われつつある「風習・しきたり」。
それは、時に親子の絆を深め、時に人と人の縁を繋ぎます。
人と人とを繋ぐ花嫁のれん
祭りや、正月などおめでたい時に飾る地域・家もありますが、嫁入り時の仏壇参りに使ったきり、箪笥に大切に大切にしまっている方がほとんどです。
せっかくの花嫁のれん、年に一度だけみんなで飾ってみてはどうか、そんな女将さんたちの声掛けで2004年に始まった、ここ一本杉通りの『花嫁のれん展』は毎年春、昭和の日~母の日まで開催されています。
県内外から多くの方が花嫁のれんを観に七尾・一本杉を訪れ、そこでまた幾つもの出会いやご縁が生まれ、花嫁のれんが人と人とを繋ぐ架け橋となっています。

平成22年 第7回花嫁のれん展の様子